【探究課題】平和な世界を実現するための世界遺産の役割について探究し、提案してみよう
世界遺産×SDGsチャレンジ!2025年度の探究課題の一つ「平和な世界を実現するための世界遺産の役割について探究し、提案してみよう」について、NPO法人世界遺産アカデミー会長、第8代ユネスコ事務局長の松浦氏の講演を参考に、課題解決策を考えてください。
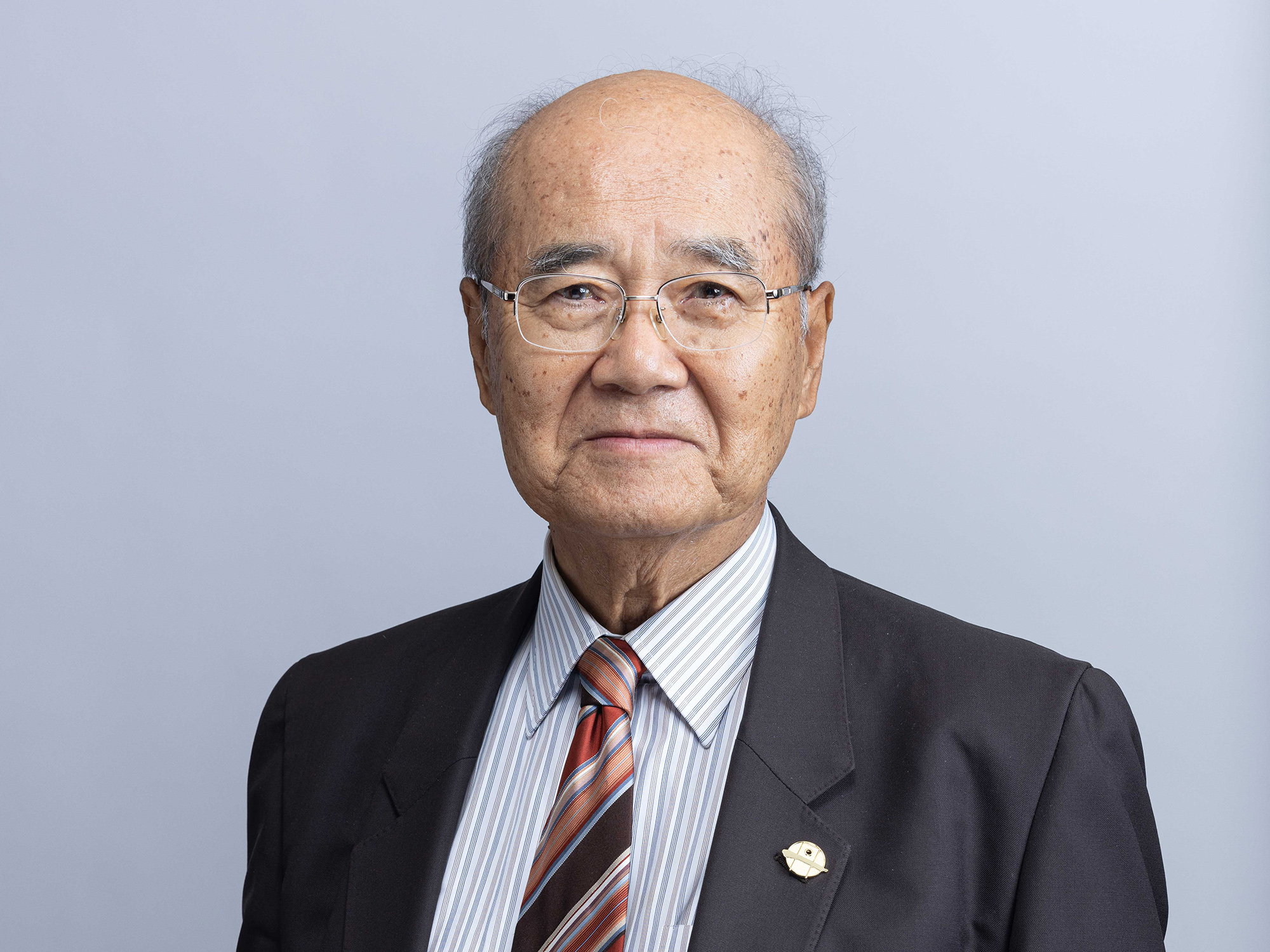
NPO法人 世界遺産アカデミー会長
第8代ユネスコ(国連教育科学文化機関)事務局長
松浦 晃一郎氏
2025年2月17日(月)『NPO法人 世界遺産アカデミー設立20周年記念講演会』の講演内容より一部抜粋。
私が最初に世界遺産に関わったのは、1998年11月から12月にかけて京都で開催された世界遺産委員会の時です。私は外務省にいまして、それまでにさまざまなポストを務めてきたのですが、世界遺産に直接関係する仕事はしていませんでした。1972年に世界遺産という制度が出来て、私はもともと歴史的な建造物を訪れるのが好きでしたから関心は持っていたのですが、専門的なことを勉強したのは1998年の世界遺産委員会の議長を頼まれた時が初めてでした。議長をするということで1年前から勉強を始めたので、専門的な勉強を始めたのは1997年からということになります。約30年ということですね。
世界遺産委員会の議長というのは、世界遺産委員会の会期中の会議の場において議長を務めるのが主な役割なのですが、それからの1年間、世界遺産委員会の運営の責任者ということでさまざまな仕事があります。当時、私は駐フランス日本国特命全権大使を務めていたのですが、ユネスコにある世界遺産センターという事務局の所長が、何度も報告や相談にやってきていました。
この世界遺産委員会を日本が初めて京都で開いたということにはとても大きな意義がありました。というのも、日本が国内体制を整えて世界遺産条約を批准したのはとても遅く、1992年のことでした。世界遺産条約は1972年にユネスコ総会で採択されて、1975年に発効するのですが、日本の条約批准は採択から20年もかかっている。しかし、日本は世界遺産条約と全く関係してこなかったかというとそうではないです。日本がユネスコに加盟したのは1951年ですが、日本がユネスコ総会の議長を初めて務めたのが1972年にパリで開かれた総会の時です。そう、世界遺産条約が採択された時なんです。議長を務めたのは、当時の駐フランス日本大使をされていた萩原徹大使、私の大先輩です。
萩原大使が非常に力を入れて世界遺産条約を採択したのですが、もう一人、ユネスコの第5代事務局長を務めていたフランスのルネ・マウの尽力も大きかった。エジプトのナセル大統領が、ナイル川沿いにアスワン・ハイ・ダムを作るという計画を出したことで、今は世界遺産になっているラムセス2世が築いたアブ・シンベル神殿などが水没してしまうという危機にありました。ユネスコはそれを何とか救えないかと知恵を絞るのですが、単に陸に引き上げるというだけではなく、一年に2度だけ太陽の光りが神殿の奥まで届くように技術的にもしっかりしたものを陸上に作らなければならないので、とても難しいプロジェクトでした。最初、アスワン・ハイ・ダムを現地に残して神殿の周りをガラスで囲うという案もあったのですが、大勢の人が見にきて万が一ガラスが割れてしまったりすると全員亡くなってしまうのでリスクが大きすぎるために止めになりました。その中で、ルネ・マウ事務局長がいろいろな方に相談されて、歴史的に非常に価値のある建造物を守って残していく上で、当事国だけでなく世界全体が協力する体制が重要だと強く考えて動かれたことが、世界遺産の考え方の大きなスタート地点でした。アブ・シンベル神殿は、現在も残されて世界遺産に登録されているのですが、私もユネスコ時代に見に行き、こうした歴史的価値のある建造物を保存していくことが非常に重要であると改めて考えさせられました。

アブ・シンベル神殿

ロベン島の刑務所跡
世界遺産のハード面とソフト面について少し詳しくお話しします。世界遺産の中の文化遺産を見てみると、日本の文化遺産の第一号は1993年に登録された『法隆寺地域の仏教建造物群』と『姫路城』ですが、初期の文化遺産というのは「誰が見ても世界遺産だ!」とわかるくらいに、歴史的な建造物として立派なものが登録されてきたのですが、少しずつそうしたハード面だけでなく、ソフト面も勘案した世界遺産を誕生させようという動きが出てきました。
例えば、南アフリカのアパルトヘイトの時代にネルソン・マンデラが過ごした監獄がいまだに残っているのですが、これを単に見ただけでは、その価値がよくわからない。日本の法隆寺や姫路城の例を挙げましたが、フランスのパリでもノートル・ダム大聖堂やエッフェル塔のように、誰が見てもすぐに世界遺産としての価値がわかるものが登録されているのに対し、監獄というだけではとても世界遺産にする価値がわからない。
その前には日本でも『広島平和記念碑(原爆ドーム)』が世界遺産に登録されています。原爆ドームはやはり、世界で最初の原子爆弾の被害を受けた「ヒロシマ」を象徴するドームということで、初めて価値がある訳で、そこに歴史的価値がある。もし、そうした背景を知らないで原爆ドームをご覧になったら、「なんでこれが世界遺産なんだ?」と思われると思うのです。
ご存じの通り、世界遺産には登録基準が①から⑩まであって、その中の①から⑥が文化遺産、⑦から⑩が自然遺産に当てはまるものになっています。文化遺産の登録基準をもう少し詳しく見ると、実際には①から⑤がハード面を対象にしていて、⑥がソフト面、いわゆる世界遺産の歴史的なバックグラウンドに関する点を対象にしています。
『広島平和記念碑(原爆ドーム)』の世界遺産登録に際しては、残念ながらアメリカと中国が反対しましたが、最終的には登録基準⑥で採択されました。ハード面を評価する①から⑤は適用されず、ソフト面を評価する⑥だけが適用されたんです。ここに原爆ドームの世界遺産としての価値がよく表れています。しかし、これに対してもやはり反発があって、登録基準⑥のみで世界遺産に登録するのはいかがなものかという意見もありました。不動産を登録する世界遺産は、ハード面を評価するものだという考え方が根強かったためです。そのため、文化遺産を登録するときには、登録基準⑥だけでなく、①から⑤のうちのどれか1つも一緒に当てはめないといけないというルールができてしまった。幸い、原爆ドームの世界遺産登録は良かったのですが、ネルソ・マンデラの監獄を含む『ロベン島』の時はその点で議論がもめましたが、平和のための記録として何とか登録しようと最終的に、登録基準⑥に「時代の証明」の登録基準③を合わせて世界遺産登録となりました。その後、世界遺産委員会でも議論が行われて、今は登録基準⑥だけでもいいのではないかということになっています。『ロベン島』はまさにその狭間だったわけです。
※登録基準についてはこちらの記事も参照(https://www.sekaken.jp/sdgs_challenge_2025/theme-4/)
※登録基準⑥は2005年の世界遺産条約履行のための作業指針の改定で、「他の基準とあわせて用いられることが望ましい」に変更された。
日本はスタートは遅かったですが、日本が世界遺産条約に参加してからは積極的に活動に関わって、世界遺産委員会のメンバーにも当選しました。世界遺産委員会のメンバーでないと議長国にはなれないのですが、その議長国になったので、京都で世界遺産委員会が開かれ、私が議長になりました。
今後の世界遺産のことを考えると、世界遺産の数もずいぶん増えて地域も拡大していますが、まだまだ地域的な偏りがあります。196ヵ国がメンバーですが、世界遺産がない国が20数か国もあります。世界遺産は、西欧中心的なところから世界的に広がりましたが、それでもまだまだ広がりが足りません。そうした意味で、地理的な拡大と内容の多様化が課題だといえます。
もう一つ付け加えると、世界遺産候補を選ぶ段階は、日本でも最初は政府主導で、政府が日本各地の文化財や自然の中からどの遺産を世界遺産に推薦するかを選定していました。しかしそれでは限界があるということで、2008年頃から地方、といっても地方の公共団体が中心となって選んだ遺産を取り上げるという方法になってきています。この方法の良い点は、地元がしっかり持ち上げる、地元の住民たちが力を合わせて持ち上げるということです。例えば、私は『佐渡島の金山』の登録活動に最初から噛んでいて、帰国してからはずっと推進に協力していたのですが、『佐渡島の金山』で感心したことがあります。佐渡島はもともといくつかの町村があったものが佐渡市にまとめられたのですが、そこの人たちが金山を世界遺産にしようと団体を作って推進したんです。もとは金銀山を世界遺産にしようとしていたものを、私が助言して金山に絞ったのですが、地元の一般の人たちが登録に力を合わせるということが非常に重要で、素晴らしいことだなと感心しました。
2025年2月17日(月)喜山倶楽部(東京都千代田区)
『NPO法人世界遺産アカデミー設立20周年記念講演会』講演内容より一部抜粋


