【探究課題】佐渡市の持続可能な街づくりを考えよう
世界遺産×SDGsチャレンジ!2025年度の探究課題の一つ「佐渡市の持続可能な街づくりを考えよう」について、新潟県観光文化スポーツ部文化課世界遺産室にお話を伺いました。記事を読み、課題解決策を考えてください。
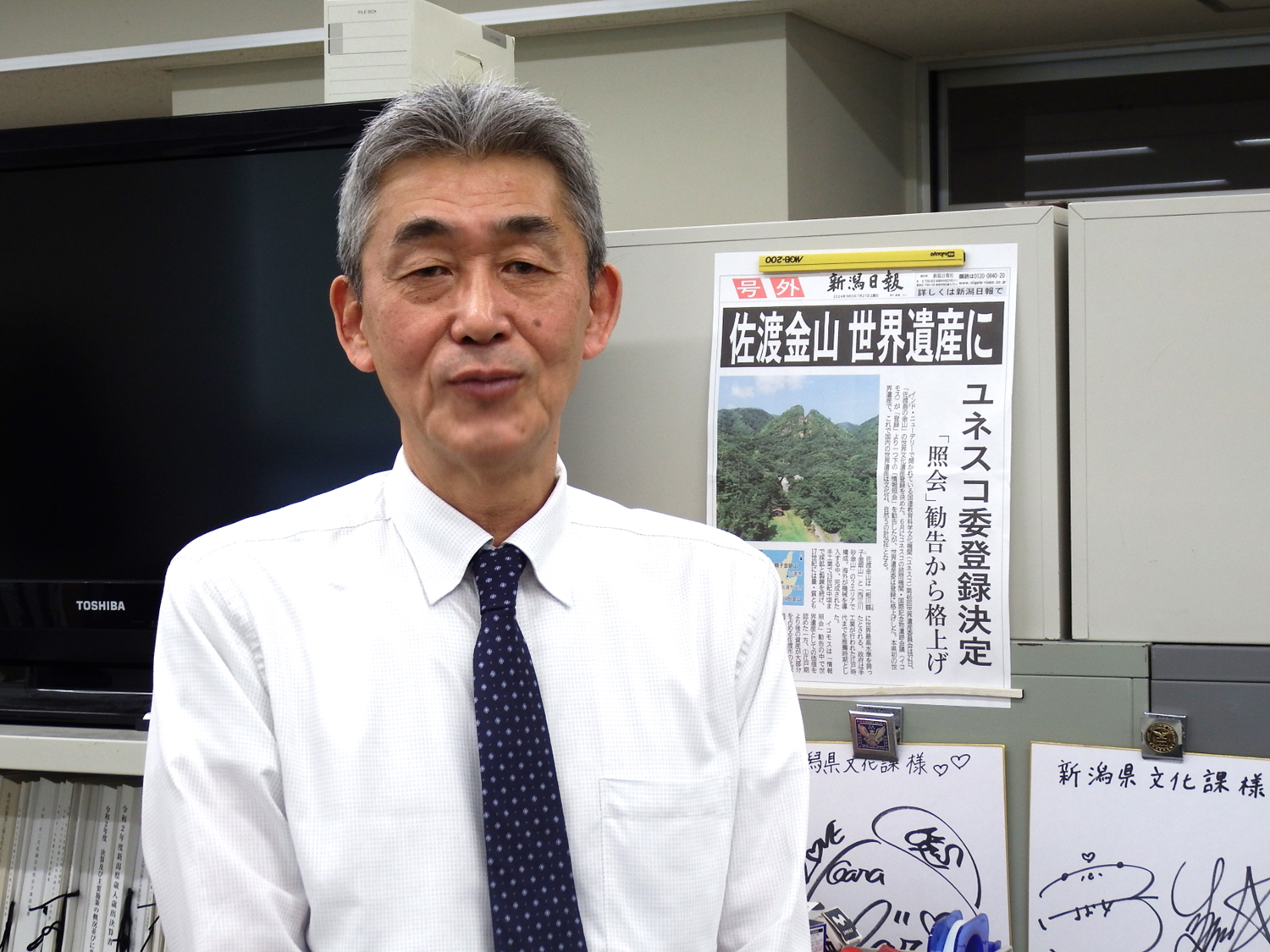
新潟県観光文化スポーツ部文化課
世界遺産室長
滝沢 規朗さん
昨年7月に世界遺産に登録された「佐渡島(さど)の金山」の価値を、しっかりと未来に継承していくために、さまざまな取り組みを行っています。個々の資産の保全や環境整備といったハード面の整備はもちろんですが、それだけでは不十分です。単に「守る」だけでは、未来にその価値を伝えていくのは難しいと感じています。「佐渡島の金山」の価値を多くの方々に知っていただくための普及活動にも力を入れ、佐渡市さんとも連携しながら、一緒に取り組んでいます。
佐渡市は新潟県にある市ですが、実は歴史的に見ると、少し特別な背景があります。古代、日本で国の仕組みが整い始め、戸籍や税制が導入されていった時代、現在の新潟県本土側は「越後国(えちごのくに)」と呼ばれていました。一方、佐渡は「佐渡国(さどのくに)」という独立した一つの国だったのです。つまり、同じ新潟県内でも、かつては別々の国として存在していたわけです。その後、時代が進むにつれて、佐渡と本土側が統合され、現在の新潟県となりました。佐渡島は離島としては非常に大きく、面積は約855平方キロメートル。これは東京23区や、瀬戸内海にある淡路島の約1.5倍にあたります。人口は現在5万人を下回っていますが、かつては10万人を超えていた時期もありました。平成の大合併以前は、島内に10の市町村がありましたが、平成16年に合併し、現在は「佐渡市」として一つの自治体になっています。
佐渡市には世界遺産に登録された鉱山があります。登録されたのは2つのエリアと3つの鉱山です。1つ目のエリアは「西三川(にしみかわ)」で、切り崩した山の土から砂金を採る地域として知られています。2つ目のエリアは「相川 鶴子(あいかわ つるし)」で、岩盤に含まれる金の鉱脈を掘り出し、粉砕して金を取り出す方法が行われていました。「相川金銀山」と「鶴子銀山(つるしぎんざん)」の2つの鉱山から構成されています。つまり、世界遺産に登録されたのは、西三川の砂金山、相川金銀山、鶴子銀山の3つの鉱山です。江戸時代、日本は鎖国をしていたため、海外の技術に頼らず、自分たちの知恵と工夫で金の採掘と精錬を行っていました。その結果、非常に高い技術に発展し、世界的にも価値があると認められました。こうした歴史と技術が評価され、世界遺産に登録されたのです。

道遊の割戸(新潟県撮影)

砂金(個人蔵)
世界遺産に登録されたことで、佐渡や佐渡金山の価値を多くの人に知ってもらう機会が増えました。登録後は実際に現地を訪れる人も増え、佐渡金山のガイダンス施設や見学施設の入館者数は、令和6年度には前年の約1.25〜1.3倍に増加しています。佐渡は島なので、船で渡る必要があり、訪問人数には限りがありますが、それでも多くの方が関心を持ち、来島して資産を見てくださっているのは大きな変化です。また、注目が集まったことで、佐渡に住む人々の意識にも変化が見られ、「しっかり守っていこう」という保護の意識が少しずつ根づいてきていると感じています。世界遺産に登録されたということは、その価値を未来に継承していく責任があるということでもあり、こうした意識の変化も、登録によってもたらされた大きな成果の一つだと思います。
佐渡市の魅力は一言では語りきれないほどたくさんあります。まず自然がとても豊かで、海も山もあり、四季折々の風景が楽しめます。食べ物も魅力の一つで、新鮮な魚介類や山菜、果物など、地元の食材を使った料理はどれも美味しいです。また、佐渡には多くの文化財が残っており、今も地域の中で大切に受け継がれています。離島である佐渡は、昔から船を通じてさまざまな文化や物資が行き交い、外からの文化を取り入れながら、独自の文化を育んできました。そうした背景があるからこそ、佐渡には「島全体が博物館」と言ってもいいほど、貴重な文化財が数多く残っています。自然、食、歴史、文化――どれをとっても魅力にあふれた島、それが佐渡市です。
佐渡市は「SDGs未来都市」にも選ばれており、世界遺産登録をきっかけに、地域に良い循環が生まれることが期待されている一方で、地方ならではの課題も抱えています。特に少子高齢化が進み、人口が少しずつ減っていることは大きな問題です。この人口減少は、世界遺産の保全にも影響を及ぼします。資産を守るには、日々の見守りや草刈り、清掃といった環境整備が欠かせませんが、担い手が減っているのが現状です。こうした状況が続けば、資産の劣化や価値の低下にもつながりかねません。だからこそ、地域が元気になり、多くの人が関わることが大切です。佐渡を訪れ、資産を見て楽しんでもらうことが、地域の活性化や世界遺産の保全にもつながります。こうした好循環をどう作っていくかが、これからの大きな課題です。
▼佐渡市のSDGs未来都市についてはこちら
https://www.city.sado.niigata.jp/site/sdgs/
先ほども少し触れましたが、佐渡の資産を紹介する施設についてお話しした通り、観光客の増加は確実に感じられます。佐渡へ行くには基本的に船を利用する必要がありますが、最近ではその利用者数が大きく増加しています。特に新潟市と佐渡の両津港を結ぶ航路は、黒字化しており、観光の活性化が地域経済にも良い影響を与えていると考えられます。具体的な経済効果の数値は明言できませんが、地域の方々からは「観光客が増えた」との声も聞かれます。佐渡は観光の繁忙期と閑散期が明確で、特に冬は日本海の荒波により船が欠航することもあり、訪れるのが難しい時期です。ただ、3泊4泊などの長期滞在で冬の佐渡を楽しむスタイルは、今後の提案として有効だと考えています。
一方で、観光の増加に伴う課題にも目を向ける必要があります。佐渡ではまだ「オーバーツーリズム」とまでは言えませんが、来訪者が増えることで地域住民の生活に影響が出ないよう配慮することが重要です。また、観光客の増加により自然環境への影響も懸念されます。希少な鳥「トキ」が生息する佐渡では、多くの人の努力により自然が守られてきました。観光客の皆さんには、マナーを守り、立ち入り禁止区域に入らないなど、基本的なルールを守っていただく必要があります。観光客が快適に過ごせると同時に、地域の方々の暮らしも守られる――そのバランスをどう取るかが、重要だと考えています。

相川上町の鉱山町と奥の山々は相川金銀山の採掘域
もし上記に挙げた様々な課題にしっかり対応せず、何の対策も取らなければ、まず影響を受けるのは佐渡で暮らす住民の皆さんです。観光客が増える中でマナーが守られなかったり、生活に支障が出たりすると、住民の皆さんが不快に感じるだけでなく、観光客も気持ちよく過ごせなくなります。その結果、観光の制限が厳しくなり、佐渡の魅力を十分に楽しんでもらえなくなるという悪循環が生まれる可能性があります。さらに、立ち入り禁止区域への侵入などで世界遺産の資産が劣化すれば、未来への継承にも悪影響が出ます。また、人口減少や担い手不足により、資産を守る人や環境整備を行う人が減ると、適切な管理が難しくなるとともに、価値の発信力も弱まります。世界遺産の価値が損なわれるなどの最悪の事態は、絶対に避けなければなりません。
高校生や中学生の皆さんに、ぜひ考えてほしいことがあります。佐渡島の金山が世界遺産に登録されたことは、日本にとって誇らしい出来事であり、皆さんの身近にある世界の宝です。この貴重な資産を未来に引き継ぐには、課題に向き合い、工夫することが大切です。たとえば「佐渡をもっと元気にするには?」「地域を楽しく盛り上げるには?」といった視点で、自由な発想で考えてみてください。皆さんのアイデアが、地域の未来をつくるヒントになります。佐渡の魅力をもっと多くの人に知ってもらい、訪れてもらうことは、地域の活性化にもつながります。ぜひ佐渡について調べ、自分にできることを考え、アイデアを私たちにも教えてください。


