世界遺産×SDGsチャレンジ!活用事例

東京家政学院中学校・高等学校
左から、塩崎 奏心さん、加田 遥さん、小口 里彩さん、村越 史佳さん
2024年度 プレゼンテーション部門
「身近な世界遺産候補を見つけ、どのように保護・保全すべきかを考えよう」最優秀賞
高校2年生の地歴探究の授業で、地理と歴史の内容をあわせた世界遺産の学習に取り組んでいました。そのなかで、総合的な探究の時間で学んでいるSDGsの取り組みとも関係があるので、チャレンジしてみようと思いました。
世界遺産の授業で学んだ内容から、日本に自然遺産が少ないこと、複合遺産は1件もないことを知りました。なので、身近な地域の世界遺産候補として日本で初めての複合遺産に登録できる自然豊かな場所として「高尾山」を選びました。調べていく中で、高尾山の年間登山者数は文化遺産の富士山を超えて世界一といわれていることが分かり、高尾山のもつ人々を惹きつける魅力に興味がわきました。
*正式テーマ名:「身近な世界遺産候補を見つけ、どのように保護・保全すべきかを考えよう」
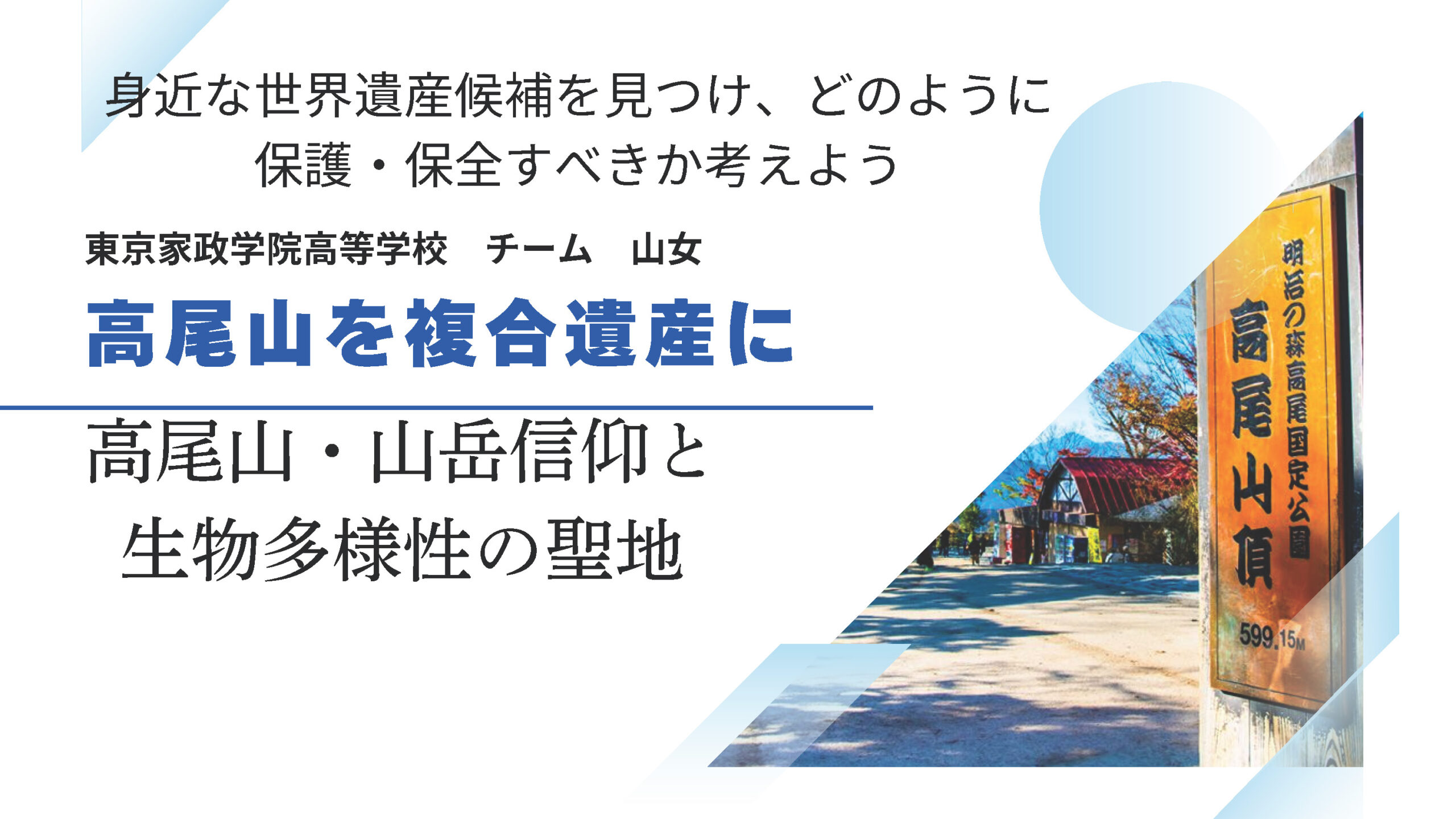
現地の課題を肌で感じるために、実際にチームで高尾山に登りました。登山中には、登山者によって踏まれた木の根がむき出しになっていたり、リフトの下にあるたくさんのゴミを見つけたり、さまざまな課題を発見することができました。同じくオーバーツーリズムが問題となっている世界遺産(日光東照宮)を訪れたチームメンバーもいました。
プレゼンテーション動画や企画書の作成では、聞き手に興味をもってもらうために伝え方を工夫しました。スライドは統一感と山をイメージするため緑をベースとして作り、1 スライド1メッセージを意識しながら要点を簡潔かつ分かりやすく伝える工夫をしました。また写真などの資料は、調べて出てきたものではなく自分たちで撮影した写真を使うことで、動画のオリジナリティを出しました。
さらに、スライド資料を長時間示して説明していると聞き手が飽きてしまうので、ペットボトルキャップを活用した“しおりの作り方動画”をプレゼンテーションに入れました。その他、ワークショップの開催などわたしたちが行動に移せることを提示したり、動画の最後では高尾山に対するチームメンバー1人ひとりの熱意を伝えました。
この体験を通して、日常的に自然への負担がかかることやごみ問題に意識が向くようになりました。SDGsの目標を活用することで、世界遺産候補となる物件の価値をどのように保護するか考えるきっかけとなったため、今後は地域の身近な社会課題について考えていきたいです。
また企画書やプレゼンテーション動画などの制作にも最後までこだわり、見やすさを追求しました。この経験を活かして、聞き手にインパクトを与えるプレゼンテーションを心がけたいと思いました。
今後の具体的な行動として、この夏に高尾山でペットボトルキャップを使ったごみ拾いワークショップを開催する予定です。SDGsのゴール番号12番「つくる責任、つかう責任」と15番「陸の豊かさも守ろう」などの目標達成に向けて、私たちにできることをやろうと思います。
学校設定科目の地歴探究の授業で活動に取り組みました。身近な世界遺産候補を高尾山に設定し、現地を訪れるだけでなく、同じくオーバツーリズムを抱えている日光東照宮にも足を運ぶなど、生の知識、教養を身につけようとする行動力は素晴らしいものがありました。
現地の“空気感”を知っているからこそ、「伝えたい」という気持ちが届くプレゼンテーションを考察し、考案したペットボトルキャップでつくるしおりの試作品を動画でまとめたり、スライド資料に頼らず、自分のことばで発信するメッセージ映像を挿入したりと工夫を凝らした内容に仕上げられました。活動では探究の進め方やプレゼン方法などの「やり方」よりもチームでの活動の中で自分がどうあるべきか、その「在り方」を追究できるよう指導してきました。今後も持続可能な社会の実現に向けて自身のあるべき姿を追究しながら学びを深めていってほしいと思います。

三田国際学園高等学校
岩泉 柚葵さん(左)、佐伯 心優さん(右)
2023年度 プレゼンテーション部門
「ネパールの水問題の解決策を考えよう」 最優秀賞
このテーマを選んだ理由は、自分達にゆかりのない地域だからこそ選びました。「ネパールの水問題」と聞いたとき、本当に何もネパールについてのイメージがありませんでした。ですが、そんな自分達の問題意識や国際社会への興味の欠如も、こういった問題を助長させているかもしれないと思い、問題を自分事にすべく選びました。
丁度、「リベラルアーツ」(総合的な探究の時間の活動)の一環で取り組むテーマ探しをしていたところ、観光名所や芸術的、自然の神秘というイメージを持つ世界遺産というテーマに、持続可能な社会づくりという目標を掲げるSDGsを掛け合わせるこのコンテストのコンセプトが、とても多角的でリベラルアーツとして楽しそうだなと思ったのも理由の一つです。
とても大変だった点は、ネパールの水問題についての情報収集です。現地の人がどのような問題に実際直面していて、どう対応してきたのか、どのような思いを持っているのかを掴むために、たくさんのサイトや水問題に関する論文を参考にしました。それでも情報不足を痛感したため、ネパール料理屋で働く在日ネパール人の方々にインタビューを行いました。この過程では、言語の壁やアポイントの取得がとても大変でしたが、良い気付きを得ることもできたので、素晴らしい経験でした。
もう一つ、プレゼンテーション動画ならではの分かりやすく伝えるという点を工夫しました。時間内に自分達の伝えたい事を効果的に伝えるため、コンパクトな構成と見やすい資料作りを心がけました。動画にする際は、編集時に音量調整をしたり、字幕や音楽をつけたりすることで「分かりやすさ」という点を意識した動画を作成しました。
「ネパールの水問題」という言葉だけ聞くと、非常に限定されているように感じますが、私たちは取り組んだプロセスに学びを得たと思っています。「世界遺産×SDGsチャレンジ!」参加前には、世界遺産検定を受検したり、調べた情報やインタビュー結果を分析したり、自分達ならではの視点で解決策の糸口を見つける機会は中々無いので、かけがえのない経験になりました。今回のように、自国ではない他国に目を向ける事で、国際的で包括的な姿勢、考え方を得ることが出来たと思います。この経験を通じて得た学びや気付きが、私達の将来への興味の広がりや、探究にとても活かされています。これからも国際的な問題を自分事に捉え、考え続けたいと思っています。
(写真:実際にネパール料理店へ赴きインタビューを行う様子)

「ネパールの水問題の解決策を考えよう」のプレゼンテーション部門で受賞した2名は、高校2年の地理探究の授業を通して「自分が知らないこと、わからないことは何か」というところから探究する方法を学んだ生徒です。インタビューを行ったことを高く評価していただきましたが、課題について問いをたて、自らの調査をもとに探究していくという手法は地理の学習においてもお手本のようです。地理の学習にとどまらず、「リベラルアーツ」(総合的な探究の時間の活動)の課題として本テーマを取り上げ、社会課題を解決しようとしたことも高く評価できます。今後もネパールのことや世界遺産の学習を通して、様々な課題について探究を続けていってもらいたいと思っています。この度はこのような貴重な機会をいただき、評価していただいたことに感謝申し上げます。

清泉女学院中学高等学校
菅野 蘭さん(左)、佐々木 心音さん(右)
2022年度 プレゼンテーション部門
「産業遺産を例に持続可能な産業のあり方を考えよう」 最優秀賞
(菅野さん)
神奈川県に住む私達が二人とも訪れたことのある、身近な世界遺産である富岡製糸場が産業遺産だということが理由の一つだったと思います。また、個人的に観光に興味があるため「世界遺産を活用した持続可能な観光を考えよう」のテーマも考えましたが、産業遺産の保全について考えたときに観光と関連付けることもできると思い、このテーマを選びました。
(佐々木さん)
2022年度のテーマの中で、「産業遺産を例に持続可能な産業のあり方を考えよう」が一番産業遺産ということで取り掛かりにくく感じたため、取り掛かりにくいからこそ自分が興味を持って取り組むことで、興味が今ない人にも面白さを伝えられるのではないかと思ったからです。また、自分が住む関東に世界産業遺産「富岡製糸場」があり、菅野さんが小学校のときに、私が2022年の夏休みに訪れていたので、何か行ったからこそ考えられることがあるのではないかと思ったことも一つの要因です。
(菅野さん)
見やすいスライドを作ることや、「フィリピンのコルディリェーラ」や「棚田」のような発音しづらい言葉を丁寧に伝えることを心がけました。
(佐々木さん)
プレゼンテーション動画を作る際に心がけたことは、まず、世界遺産や産業遺産に興味がある方にも、そうでない方にも、「聞いてみよう!」と思って、身近に感じていただけるような動画にすることです。例えば、「あの、教科書で見た赤いレンガの建物や蚕、生糸生産の風景でおなじみの富岡製糸場」や、「サッカーのワールドカップで湧いたカタールで行われた世界遺産委員会で…」という台詞で、聞き手一人ひとりが自分の記憶や興味のあることを想起しながら聞いていただけるように心がけました。また、富岡製糸場からプレゼンテーションを始め、中盤で世界の遺産に話を広げることで、日本と世界の世界遺産の共通点を感じていただき、日本と世界の繋がりに想いを寄せていただけるように、ということも心がけました。
(菅野さん)
今回発表したプレゼンテーションで提案した「グッズアイディアコンテスト」を実行に移しました。世界遺産に関するイラストを校内で募集し、そのグッズを販売することで世界遺産への関心を高め、訪れてもらうきっかけをつくるというもので、グッズ販売で得た利益は全額産業遺産である富岡製糸場の遺産保護のために寄付するという活動です。コンテストの企画、グッズ販売の経験はなかったため難しい試みでしたが、この提案を実行に移したことでさらに産業遺産を含む世界遺産への自分たちの関心が高まり、イラストを応募してくれた生徒やグッズを購入してくれた生徒、先生方の関心も誘うことができました。
今回の「世界遺産×SDGsチャレンジ」を通して得た知識や経験を活かし、これからも持続可能な産業のあり方を考えていきたいと思います。また、世界遺産についてより深く学び、多くの人に広めていきたいです。

(佐々木さん)
まず、世界遺産×SDGsチャレンジ!のプレゼンテーションを行うことを通して、より世界遺産そして世界産業遺産に興味が湧き、多くの人に広めたいと強く思いました。そして、産業遺産を始めとする世界遺産の保護のためには、世界遺産を難しいものとしてではなく、親しみやすいものとして捉えてもらえるように、皆が参加しやすい活動をするのが良いのではないか、という学びを得ました。
この学びを活かし、プレゼンテーション内で提案した、世界遺産グッズアイディアコンテスト(校内で世界遺産のイラストを募集し、学校内の投票でグッズ化するデザインを決めるコンテスト)と世界遺産グッズ販売(校内と学校説明会にて、コンテストで決定した3作品をデザインしたバッグ、ポーチ、キーホルダーを販売)を行わせていただきました。4月の企画から販売するまで、想定していたよりもやるべきことが多かったり、校内での周知がうまくいかなかったりして大変な時もありましたが、続けることができたのは、世界遺産を身近に感じてもらいたい、という世界遺産×SDGsチャレンジ!での学びから派生した思いがあったからこそだと思います。企画時から今まで温かくご指導下さっている先生と、この活動にご理解をいただいて、協力してくださっている方々皆様に感謝したいです。これからもこの思いと感謝を胸に、世界遺産にもっと多くの人が興味を持ってもらえるように活動していきたいです。
「産業遺産を例に持続可能な産業のあり方を考えよう」というテーマがあったことで、世界遺産の中でもまだ認知度の低い「産業遺産」にじっくりと触れる貴重な機会となりました。この難しいテーマに挑戦した2人は、「どのようにしたら産業遺産への関心を幅広い人に持続的に持ってもらえるか」というサブテーマを掲げて取り組みました。単に世界遺産が抱える課題を考えるのではなく、解決へのアプローチに潜む課題にも目を向ける姿勢に、大変感心しています。また、公募した世界遺産デザインの商品化や販売に際しては、マーケティングの知識・手法を専門家から教えていただき、世界遺産を入り口として別の学びの扉を開くきっかけにもなりました。今回、このような価値のある経験をする機会がいただけたことに感謝しております。

青森県立青森南高等学校
右から、原田 愛子さん / 黒田 瑞希さん / 葛原 沙紀さん
2021年度 プレゼンテーション部門
「戦争の記憶の継承方法を考えよう」 最優秀賞
3人で世界遺産検定を受検したときに「負の遺産」の存在を知り、原爆ドームに興味をもったことがきっかけです。
私たちの住む青森県でも、太平洋戦争のときには空襲がありましたが、若い人達にとっては遠い昔のことであり実感が伴いません。いま、日本の全人口のうち約9割が戦後生まれと言われています。戦争の記憶を継承するためには、私たち若い世代が戦争のことを知り、より若い世代に伝えていくことが大切だと感じ、「世界遺産×SDGsチャレンジ!」への参加を決めました。総合的な探究の時間でSDGsについて学習し、SDGsの重要性を実感していたことも、参加理由のひとつでした。
初めての動画作りでしたが、見る人を惹きつけられるようにBGMをつけたり、イラストを多く使うなどの工夫をしました。また、動画内の資料で使う色は、私たちが特に深く研究したSDGsの目標16番『平和と公正をすべての人に』の青色を基調とすることで統一感を出しました。
動画を作るにあたっては戦時中に空襲を体験した人や遺族の方々にお話をうかがったのですが、戦争の悲惨さを知るにつれて「この経験は、自分たちが語り継いでいかなければいけない」という思いがより強くなりました。
自分たちが学んだことをさらに下の世代に伝えるべく、中学校を訪問し「戦争の記憶の継承の重要性」と題した出前授業を行いました。出前授業では世界遺産の理念についても話をしたのですが、中学生からは、「戦争をなくすには、まず相手の国のことを知る必要があるのではないか」という意見がありました。他国のことを知る、多様性を認め合うことの重要性が中学生にも伝わり、嬉しかったです。
今回の「世界遺産×SDGsチャレンジ!」への参加を通じ、今も世界のあちこちで続いている紛争や争いにも目が向くようになりました。世界の問題にもっと関心を持ち、知識や理解を深めるとともに自分にできることは何かを常に考えていきたいです。

世界遺産が抱えているさまざまな課題を探究することでSDGsの各目標を理解し、世界の多様性を学び、主体的に行動する良い機会となりました。今回3人は世界遺産検定を受検したことで「負の遺産」を知り、広島だけでなく地元の青森でも空襲があったことに着目しました。青森空襲体験者の方々に自分たちでアポイントメントをとって取材に出かけ、興味・関心から探究し、プレゼンし、実践するところまでやり遂げました。実際に中学生と議論することで新たな課題や改善を加え、まだまだ探究しています。このような貴重な機会をいただけたことに感謝するとともに、卒業後も探究心をもって何事にも取り組んでほしいと思っています。


