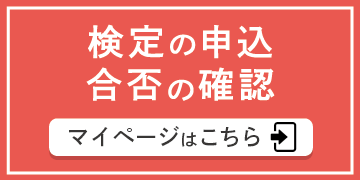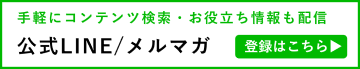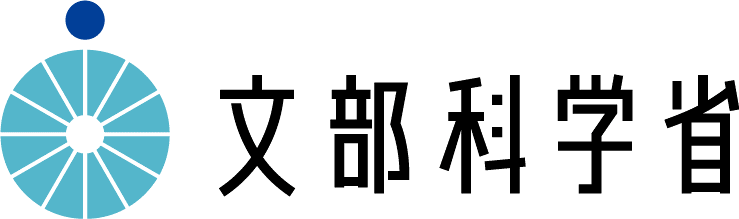最終日の世界遺産委員会の報告が遅くなりすみません。最終日はスーツケースを持ったまま参加し、閉会後はその足で空港に向かい、バタバタと帰国しました。
世界遺産委員会の最終日は、書記であるルワンダのジョエル・ブキャナンさんから全体の報告があり、彼女を労う温かい雰囲気の中で決議されました。
しかし、初日のオブザーバーの承認のところで、直前で修正案が出され、十分な確認も議論もできないまま、あるNGOを削除する修正案で決議されたことについて、イタリアが決議から外れる旨のコメントがあり、インドなどのいくつかの国がイタリアに賛同しました。これは、そのNGOが世界遺産委員会の議論を政治問題化するコメントを繰り返しており、名前を変えながら同様の行為をしているとトルコから指摘があった団体です。初日にもベルギーやオランダなどから、直前の修正案で十分議論ができないまま決議されたことについて、プロセスが正しいとは言えないのではないかとのコメントがあったものでした。
その後は、アソモ世界遺産センター長から議長や委員国、スタッフへの感謝や労いのコメントと共に、この世界遺産委員会で多国間主義が再度示されたことや、今後も世界遺産活動に積極的に参加してほしいという挨拶があり、各委員国を務めた国からも感謝のコメント等が出されました。
今回の世界遺産委員会で任期を終える国は、21カ国中12カ国(※)あり、日本もそこに含まれています。今年ユネスコ総会内で開催される世界遺産条約締約国会議で、新たな委員国が決まります。
最後は、委員国の代表全員で写真撮影があり、定時の18時より少し早く、12日間の世界遺産委員会が無事に終了しました。
今回の世界遺産委員会に参加して、政治的な発言はあるものの、基本的には世界遺産のOUVと保護の話がメインであり、政治的な発言はほとんど深堀りされないこと、国際会議らしくルールを非常に重視すること、すべての国が平等なユネスコらしく各国の発言が尊重されることなどを感じました。最終日もパレスチナとイスラエルのやりとりがありましたが、双方がコメントしたところでその話は終わりました。
また気候変動や先住民の権利に言及されることが多く、どの遺産にも共通する話題であることや、アフリカの遺産の保護体制の確立や登録が共通課題であること、保全状況報告が行われた遺産のバランスから見て、まだまだユネスコの資金・人的リソースが西欧諸国に重きが置かれているように捉えられていることなど、世界遺産活動の現状についても垣間見ることができました。
パリ滞在中は、24時間中23時間は室内にいて、議論を聞いたり資料を読んだり、文章を書いたり、メモを読み返したり、日本の仕事をしたり(7時間の時差のために常に仕事している感じ)していて、本当にぐったり疲れましたが、大好きなパリで過ごすことができて、楽しく充実した日々でした。
帰国後は、登録されたばかりの韓国の『盤亀川沿いの岩面彫刻群』が洪水の被害にあったり、アメリカ合衆国がまたユネスコ脱退を表明したり、まだ世界遺産委員会の延長上にいるような気がします。
振り返ってみると、アメリカは世界遺産委員会の審議初日に、2001年以降で1億2,500万USDを文化財の保護に投資し、そのうちの1つを含む『カンボジアの記憶の場:抑圧の中心から平和と反省の場へ』が今回審議されることや、今後もリーダーシップを発揮して最新技術を用いながら遺産保護に協力していくこと、次の世代のために各国と協働して遺産の保護を行っていくことなどをコメントした後は、2度と発言することはなく、存在感は全くありませんでした。
トランプ大統領が誕生したことで、ユネスコ脱退は予想されたことではありますが、ユネスコの活動全体を見ると反イスラエルに偏ってる感じはしないですし、小さな一部分を言いがかりに全体を否定し、多国間主義から離れることが「自国ファースト」だとしたら、「自国ファースト」の主張もずいぶん近視眼的な気がします。確かにアメリカに頼りすぎなところもあるので、そこは見直していかないといけないですが。
今回の世界遺産委員会のまとめと、遺産名の仮訳は、世界遺産検定HPに掲載されていますので、そちらをご確認ください。
2025年新情報
※ 任期を終える12カ国:アルゼンチン、ベルギー、ブルガリア、ギリシャ、インド、イタリア、日本、メキシコ、カタール、ルワンダ、セント・ヴィンセント・グレナディーン、ザンビア


(2025.07.24)